- ジェリーが倒れた死体を見つける。死体は高級ウイスキーの酒瓶を持っていた。
- 死体が突然動き出し、自分の酒だと言いながらジェリーを脅す。
- ジェリーは酒を盗むつもりが、アイカに見つかり心が和む。
6枚のコイン

6枚のコイン2024-05-07 「無期迷途」運営チームPart.01今年最後の月の初日は縁起の良いものではなかった。朝早く起きたジェリーは、フォルトナ劇場の隣にある赤い花柄のレンガの街角で誰かが死んでいるのを見つけた。 ここは、ニューシティのホームレスたちが気に入っている場所の一つだ。突き出たレンガが風をよく遮ってくれる上に、劇場に出入りする金持ちを観察しやすいからだ。そうした紳士たちは特に家族がいる場合、年末になると優しくなることが多い。彼らの靴を磨いたり、コートの裾を持ち上げたりすれば、簡単にチップを稼ぐことができる。ジェリーはこの寒く美しい季節に向けて、自分の悪臭が紳士たちに影響しないよう何度も上着を拭いた。彼らのポケットからもっとコインを引き出すためだ。しかし、隅に横たわる死体を見た瞬間、この素晴らしい願いが全て打ち砕かれた。彼は倒れている死体に近づき、「おい」と言いながら蹴った。 その人は少しも動かず、綿入れの服が泥で汚れている。髭は黄色い落ち葉に覆われ、手足は氷のように凍っていた。その傍には、中身が半分こぼれている酒瓶が落ちている。ジェリーは瓶も蹴り飛ばしたくなったが、考えた末にしゃがみこんでそれを見た――10年熟成された高級ウイスキーだ。値段は決して安くないだろう。ここで凍死している不運な金持ちの紳士は誰だろうか。ジェリーは周囲を見回して誰にも見られていないことを確認し、酒瓶を取り上げようとした。 しかしその瞬間、倒れていた死体が突然動き出し、手袋をした手が彼の手首にかかった。「これは俺の酒だ、泥棒」ジェリーは驚いて罵り、その手首から自分の手を引き抜いた。男はうめき声を上げながら寝返りを打ち、また気を失う。どうやら寝言だったようだ。ジェリーは深呼吸をした。たとえ生きていても、この紳士にはもうこの酒は必要ないだろう。だがジェリーは違う。彼はこのような高価な酒を飲んだことがない。こうした寒い日には、身体を温めるために酒を飲むべきだ。飲み終わったら、酒瓶に偽の酒を入れればいい。高く売れるだろう。 酒瓶を持って立ち去ろうとした時、傍から爽やかな声が聞こえた。「ジェリー、キミ酒を盗んだでしょ」ジェリーが驚いて振り向くと、フォルトナ劇場の前でいつもサックスを吹いている少女、アイカがいた。彼の心がそっと和らぐ。この少女はいつも妹を思い出させるのだ。もし彼女がまだ生きていたら――10年前の冬に連れ去られていなければ、アイカと同じくらいになっていただろう。 「ちょっと飲むか?」彼はアイカに向かって酒瓶を振った。アイカは首を横に振って駆け寄り、地面に横たわっている「死体」の額に触れる。「ジェリー兄さん、この人このまま寝てたら凍死しちゃうよ」ジェリーは不機嫌そうに彼女を叱った。「余計な心配するな。俺だってもうすぐ飢え死にするんだ。こいつのことなんか、どうでもいいだろ」 しかし、アイカが酔っぱらいの大男を懸命に動かそうとしているのを見て、彼は思わず手を貸した。二人で声を上げながら、死体のような酔っ払いを裏口から劇場前の公衆トイレまで引きずっていくと、ジェリーはこう言った。「俺が助けられるのはここまでだ。またこんなことがあっても、絶対俺に頼むなよ」 アイカは、彼の言っている意味が全く理解できていないように嬉しそうに笑う。「ありがとう、ジェリー。お礼にサックス吹いてあげよっか?」「いや、大丈夫、大丈夫」アイカがサックスを吹くと言った途端、ジェリーは逃げ出した。 アイカの音痴は劇場周辺では有名な話だ。この一角はホームレスに人気があるため、ホームレス同士の諍いがよく起こっていた。しかしアイカが近くでサックスを吹くと、誰もが黙って耳を塞ぎ、逃げていく。アイカに好感を抱いているジェリーでさえ、1分以上彼女のサックスを聞く勇気はなかった。彼が1ブロック先まで走った時、恐ろしい音が聞こえてきた。アイカはやはりトイレでサックスを吹き始めたようだ。 「な、なんだこの音は?」酔っ払い男はサックスの音で目を覚まし、恐る恐るアイカを見る。男が起きたのを見てアイカは演奏を止め、嬉しそうに握手を求めた。「サックスだよ。アタイはアイカ。キミの名前は?なんでここにいるの?」すると酔っぱらい男は電気に触れたように手を引っ込め、地面を探り始める。「俺の酒はどこだ?」「ジェリーが持っていったよ」ジェリーもこの酔っ払い男もそうだが、アイカには人々の酒への執着が理解できない。「こんな天気なのに外で酔っ払ってるのは危ないよ!」「お前に俺の何が分かる?」酔っ払い男は、アイカが理解できないような下品な言葉で悪態をついた。「スリ、ウジ虫、クズ……」彼はしばらく怒った後、凍えた手をコートのポケットに入れ、中を探ってコインを1枚取り出した。「ジェシカ、頼む。酒を1本買ってきてくれ」「アタイはジェシカじゃないよ」アイカは受け取らず、大きな目をパチパチとしながら彼を見る。酔っ払い男は、赤く染まった眠そうな目で彼女をじっと見つめ返した。「じゃあ、お前は誰だ?」 「アタイはアイカだよ、おじさん」アイカは辛抱強く答える。「一番安いお酒は6ディスコイン。でもアタイはそんなにお金持ってないから、一緒に路上パフォーマンスで稼がない?」 「クソッ、貧乏なガキが金をせびりやがって」酔っ払い男はそう呟くと、コインを投げ捨て再びタイルの上に倒れ込んでいびきをかき始めた。倒れたことで泥だらけの足跡が身体についてしまったが、彼は気にしないだろう。アイカは慎重にコインを拾い上げ、サックスをしまった。もうすぐ今日の劇場公演が始まる。入り口で仕事をしなければならない。 休日のせいか今日は大勢が劇場に来ており、アイカもお祭りムードを感じていた。特に、劇場の外に設置された松の木の大きな星飾りは、冷たい風が吹いても温かい光を放っている。それを見ていると、アイカの心も温まった。その時、親切な人が彼女にチョコレートの入った袋を渡した。「いい子だな、サックスも上手だ。もう吹くのを止めてくれ」 大勢の人が来たため、アイカは午後の間ずっとサックスを演奏し、コインを2枚稼いだ。そして、太ったサムおじさんからパンを買った。焼きたてのパンは1個1ディスコインだが、一晩経ったパンは1ディスコインで3個買えるのだ。サムおじさんは、アイカのためにパンを詰めながらこう言った。「新しい酔っ払いが来たんだろ?あの人、なんだか落ちぶれた金持ちに見えるよなぁ。でも怖いもの知らずだよ。今朝、ピッピたちと喧嘩をしてた時に唯一高そうなスーツをひったくられてたんだ。そしたらあの人、焦る様子もなくただ酒をねだって寝ちゃってさ。あんまり近づかない方がいいぞ!」 アイカはトイレで寝ている酔っぱらい男を思い出し、首を横に振った。「ううん、あのおじさんすごく礼儀正しいよ」 彼女は6個のパンを抱えて、あの酔っ払い男の元へ向かった。酔いが醒めたらしい男は、劇場の外のベンチにぐったりと座っている。他のホームレスたちは既に、物乞い、靴磨き、コートの裾を上げる手伝いなど、それぞれに使う道具を広げていた。ただ一人、彼だけがまるで偶然通りかかったように、微動だにせず無関心に座っている。しかし、身にまとうみすぼらしい服が全てを物語っていた。どれだけ豪奢な黄金の世界から来たにせよ、彼は長い間そこに戻っていないのだろう。そして、これからも戻ることはないはずだ。 「パンを食べて」アイカは彼にパンを渡した。彼の目がゆっくりとアイカに向けられ、彼女に焦点が合う。「お前は誰だ?」「アイカだよ」アイカは全くイライラした様子を見せない。「ここの冬は厳しいから、過ごすのは大変だと思う。でも大丈夫。アタイと組んで路上パフォーマンスをすればいいさ。アタイがサックスを吹くから、キミはお金を数えて。取り分は半分ずつね。キミの名前は?」 「俺に構うな」酔っ払い男の顔には疲労が滲んでいる。「どっか行け」アイカは数歩離れ、振り返った。「ハリアーおじさんたちが、炊き出しのスープを貰いにシェルターに行ってるよ。熱々なんだ。一緒に行かない?」「シェルター?ここいらの泥棒やチンピラどもと一緒に、恵んでもらった飯を食えってか?」酔っ払い男は怒鳴りながら、アイカを殴ろうと拳を上げる。しかし、通りかかった別のホームレスが彼に唾を吐いてこう言った。「あんた何様だ?小便を鏡にして自分の顔を見てみろ」 酔っ払い男は立ち上がり、喧嘩を売ろうしているようだったが、結局震えて椅子に座り直した。そのホームレスは皮肉っぽく口笛を吹き、大股で立ち去っていく。アイカは少し狼狽えていたが、それでも期待に満ちた目で彼を見つめた。「行かないぞ」男はやりすぎたと思ったのか、態度を少し軟化させた。しかし、アイカはそう簡単には誤魔化されない。雪の中をくるりと回って、また彼に近づいた。「本当に行かないの?あそこには聖歌隊もいて、歌がすっごく上手なんだ。今年もまた『光り輝く奇跡』を歌ってくれるといいな」 彼女は聖歌隊の思い出に囚われているようで、突然歌い始めた。「美しい輝きが大地を覆い、新たな1年がまたやってきた……」 酔っ払い男は恐怖を抱いた。そして半分寝ている時に聞こえていた騒音はこの少女が発していたものだと気付き立ち上がろうとしたが、足はまだ震えている。男は最終的に、少女の歌を止める唯一の方法を思いついた。「もう歌うな……い、一緒に行くから」Part.02ジャックドーン――街を彷徨い、シェルターに収容されている全ての人の呼び名だ。ジャックドーンである前は、結婚式の司会者、首席テノール、裁判官、治安官、取締役会長など、何にでもなり得た。しかし落ちぶれた彼は、まず街に出て、空腹になると物乞いを始めるだろう。もし物乞いが苦手であれば、飢え続けて病気になり、シェルターへ送られる可能性もある。シェルターも路上と大して変わらない。3~4人の介護士では数百人もの病人の世話をすることはできず、医者もほとんど来ない。介護士は病院から薬を少し貰い、彼らに注射を打つ。やがて彼は亡くなり、介護士に白いシーツで覆われる。そこには「ジャックドーン、生年月日不詳、××年××月××日死亡」と書かれるのだ。 もし彼が物乞いをしなければ、こうした結末への歩みは加速するだろう。また、酒を好む者であればシェルターに送られる間もなく、ある静かな冬の夜、呼吸が止まって公共の焼却炉に投げ込まれてしまう。ニューシティの焼却炉で何人のジャックドーンが焼かれたかなど、誰も知らず、誰も気に留めない。 しかし、アイカはこのジャックドーンを気にかけている。だから彼はこの冬の間、焼却炉に入らずに済んでいるのだ。彼はまだどこに行けばいいのか分かっていないが、アイカと一緒にぼんやりと通りに立っていると、さほど離れていない所にフォルトナ劇場の輝く看板が見えた。 (チッ、劇場か。酔っ払ってここに戻ってきたんだな)数少ないシラフの日に、彼は自分の行動範囲に立ち入り禁止区域を設けた。その二度と足を踏み入れない場所の一つが、劇場だ。もしかすると、廃業した劇場で彼を見た人がいるかもしれない。当時は週に十数回の公演があり、その全てが完売。劇場はいつも満員だった。彼は劇場を代表する首席テノールで、観客の憧れの的だった。ステージの至る所に、バラが投げ込まれていたほどだ。極めて楽な人生だった。彼が断わらない限り、公演の終わりにはいつも舞台裏で美女とプレゼントが待っていた。しかし彼は、プレゼントを一つずつ開けようともしない。ブランド物のスーツ、時計、香水、高級車の鍵……彼は既にそうした物をたくさん持っていたからだ。紙幣は流れる水のように彼の手をすり抜け、時に1枚が数枚になり、時に束が1枚になる。そして遂に…… フォルトナが新たな大ヒット劇場となり、二日酔いの夢が覚め始めた。観客がいなければ、劇場は自然と潰れていく。誰も彼を雇おうとしなかったわけではないが、彼はもう旅回りの小劇団で歌いたくなかったのだ。元々は、サーカスの団員のようにくるくると回りながら媚びるような笑みを浮かべ、観客のリクエスト曲を歌い、頭に被ったハットを脱いで貴婦人にチップを求めるような、旅回りの小劇団からキャリアをスタートさせたはずなのに。 (いや、もう考えるのは止めよう。あんな風に歌える歳はとっくに過ぎてる)実際、ナイトクラブを離れて自分に何ができるのか、彼にはもう分からなかった。時折、彼はフォルトナ劇場で火災が起こる前から、しばらくステージに立っていなかったことを思い出す。当時所属していた劇団は業績が振るわず、多くの公演が失敗だったと囁かれていた。観客も、もう彼の周りには集まらない。それも当然だ。酒と女に溺れ、腹回りはたるみ、頬の肉はあれほど誇らしげだった顎のラインを包み込んでいる。それでも彼は、自分がまだハンサムだと確信していた。 しかし、かつて彼を応援していた貴婦人たちは皆どこかへ行ってしまったのだ。ある日、彼はポルソン夫人を道端で呼び止めたことがあった。昔、この若い夫人が彼の前でどれほど恥ずかしがっていたことか。ツアー終わりの彼の前に立った彼女は、プレゼントのように着飾り、リンゴのように顔を赤らめながら、ファンだと言っていた。しかし今では、彼の方が口ごもりながら、少し金を貸してくれないかと頼んでいる。ポルソン夫人は口を覆った。「まぁ、どうしてそんな状況に?あなたのためにシェルターを見つけて差し上げます……」 彼は逃げ出した。シェルターになど行きたくない、かつてニューシティの名優だった自分が白いシーツに包まれた惨めな死体になったことなど知られたくないと思ったのだ。彼にできるのは、酒を飲み、目が覚めたら昔の仲間たちが周りに集まっていて、夢を見ていただけだと言ってくれるのを願うことだけだ。しかし昼夜問わず何度も酒を飲み、財布が空になって高い時計や宝石や服を売り払っても、目は覚めなかった。そして昨日、彼はようやく一番安い酒が6ディスコインで、それを飲む金さえないことに気付いた。 フォルトナの輝く看板を見つめながら、彼は心の中で何かが永久に破裂したのを感じた。シェルターでは無料の医療用アルコールが盗めるらしい。アイカを追い払った後、彼は試してみようと思った。しかし、歩き始めた途端、我慢できずに腹が鳴ってしまう。アイカはこう言った。「やっぱりお腹が空いてるんでしょ。スープを飲んだらちょうどいいよ」 スープの列に並んだアイカは、二つ受け取り、一つを彼に渡す。「身体を温めてね」 器から湯気が立ち上っている。スープを一気に飲み干すと、彼はアイカから貰った冷たいパンを貪り、外の冷たい風に吹かれる落ち葉をぼんやり眺めた。ホームレスのような売り子が、風船を売っている。値段はせいぜい1ディスコインだろう。売り子は一生懸命、「風船はいかが?」と声を張り上げてはその場で風船を膨らませ、通りすがりの子供たちに押し付けていた。子供たちは楽しげに笑っている。ジャックドーンには理解できなかった。こんな安っぽい幸せを幸せと呼べるのだろうかと。 アイカはその売り子に駆け寄り挨拶をした。「マーキュリー、今日の風船は綺麗だね!」(風船なんて毎日一緒だろ?)ジャックドーンは疲れながらこう思った。しかし、売り子も嬉しそうに返している。「アイカ、今日も綺麗だね!」 (あいつのどこが綺麗なんだ?)赤毛は乱れ、衣服は棘で引きちぎられたように破れている。売り子はアイカに古い保温瓶を渡した。「さぁ、お湯をどうぞ。この容器は劇場でコーヒーを淹れるのに使われてたものなの。お湯を注げばコーヒーの香りがするのよ」アイカはそれを受け取り、嬉しそうに陶酔した表情で大きく一口飲む。そしてふと何かを思い出したように、売り子に向かって言った。「美味しいから、新入りの兄さんにも一口飲ませてあげてもいい?」 ジャックドーンはアイカがこちらに向かって走ってくるのを見て、寝たふりをしようとしたが遅かった。アイカは空になった器を奪い取り、保温瓶を彼の手に押し込む。「コーヒー飲んだことある?このお湯、本当にコーヒーの香りがするんだよ。すごく美味しいんだ」 「誰がコーヒーを飲んだことがないって?綺麗に洗ってない保温瓶にすがってコーヒーの風味を想像しないといけないなんてな」ジャックドーンはそんな皮肉を言うつもりだった。しかし、嬉しそうに目を輝かせるアイカを見ると、どうしても言葉が出てこず、保温瓶から少し飲むことしかできなかった。恐らく売り子が注いだお湯も、劇場が無料で配っている大きな鉄炉で沸かしたものだろう。錆びた鉄の匂いが保温瓶に残ったコーヒーの染みと混ざり、本当に安いインスタントコーヒーのようだった。 二人はスープとお湯を飲み干した。するとアイカは道端に布切れと帽子を置き、サックスを取り出す。寒さで顔が真っ赤になっており、帽子の上から葉が落ちていく。「もう一晩路上ライブをして、あと4ディスコイン稼いだら、キミにお酒を買ってあげられるよ」 しかし、それは不可能なことだ。アイカは計算ができないらしい。1日に2ディスコイン稼げるとしても、パンを買うだけで使い切ってしまう。それ以上稼がない限り、貯金などできるはずがない。ジャックドーンはサックスが壊れているのに気付いたが、アイカは全く気付いていないようだった。 「見せてみろ」彼はサックスを手に取り両端を見てみたが、もう直すことは難しいだろう。リードが半分欠けており、吹き口はほとんど錆びていて、曲がっているように見えた。しかし、アイカは気にする様子もなく、フォルトナ劇場の入り口を指さす。「昔、あそこでサックスを聞いたんだ。ああ、本当に素敵だったなぁ。その日に劇場の前でこのサックスを拾ってさ。アタイはサックス奏者になる運命だったんだと思う」 アイカがペラペラと喋り続けたことで、彼は彼女が長いこと路上生活をしていて、飢え死にしそうになった時、サックスを聞いたことを知った。ふと彼は思った。その日、自分はどこにいただろうかと。(どこかの劇場で歌ってたんじゃないか?そこでも誰かがサックスを吹いていた。黒人のサミーさんだったか、それとも後から来た靴磨きのデンくんだったか?)公演の後、彼らは車で歓楽街に向かったが、道端で餓死しそうなホームレスの少女に気付くことはなかっただろう。 アイカは瞬きをした。「アタイの演奏、聞きたくない?」アイカのサックスに支配される恐怖を一瞬思い出し、彼は無意識に拒否しようとしたが、彼女の嬉しそうな表情を見て頷いた。Part.03富める者にも貧しき者にも、鐘の音がいつも新たな1日の始まりを思い出させるように、新たな年はいつも予定通りにやってくる。夜の街はライトアップされ、店は新年の飾り付けをして、新たな年の到来を待っている。明日になっても大した変化はないと分かっていても、長く厳しい1年を過ごした後には、祝いの日が必要なのだ。ホームレスも、こうした日はジメジメとした寒い橋の下やシェルターのホールにはいたがらない。賑わいが新年の幸運に繋がることを願い、祭りの雰囲気に浸ろうと、混雑した通りに押し寄せるのだ。 フォルトナ劇場の夜公演が終わったばかりで、入り口は人で埋め尽くされていた。夜9時になると、道行く人の数が減り始め、通り沿いの店もほとんどが閉店し、明かりも消えている。人々は家へ帰り、家族と静かな夜を過ごすのだ。しかし、劇場の入り口だけは未だ明かりが輝いている。この神秘的な劇場では、午前0時にサプライズ公演が行われると言われている。劇場の熱心なファンにとって、年越しはもはや重要ではない。劇場の特別公演こそ、彼らが期待する新年のプレゼントだ。ホームレスたちも大勢集まっている。この劇場のオーナーは善良な人だと言われているため、新年のプレゼントのおこぼれを貰えるかもしれないと思っているのだ。 プレゼントがなくても、劇場の扉が開いているため、中から吹き出す暖かい風のおかげで、他の場所よりも暖を取れる。 アイカとジャックドーンもその中にいた。劇場の上に掛けられた大きな時計が音を立てて時を刻んでいる。人々は入り口に集まり、0時の鐘を待っていた。その時突然、群集から女性の鋭い声が響いた。「スリよ!」 人々が一斉に騒ぎ出す。劇場のスピーカーから、警備隊長の声が流れてきた。「皆さん、劇場の安全を確保するため、関係者以外は直ちに劇場から出てください。従っていただけない場合、強制的に退場していただきます」重装備した警備員の列が扉の前に現れる。そして劇場の前に群がる人々がチケットを持っている客かどうか一人ずつ確認し、ボロボロの服を着たホームレスたちを追い払った。ホームレスたちは罵声を上げながらその場を離れ、いつも陣取っている一角へ移動する。 ジャックドーンが辺りを見回すと、アイカが燕尾服を着た女性と話しているのが見えた。その女性はアイカを気に入ったようで、頻繁に微笑んでは頷き、アイカに何かを渡そうと、かがんでウエストポーチを漁る。その時、警備員の一人が彼女に向かって叫んだ。「奥様、その少女は詐欺師です。騙されないでください」 アイカは顔を真っ赤にして彼を見る。警備員はアイカに近づき腕を掴んだ。「ガキ、毎日この辺でコソコソしてるのを見かけるが、盗んだのはお前か?」 「そんなことしてないよ。この人は、近所の犬にサックスを吹いてほしいってアタイに頼んできただけさ」アイカは大声で反論する。「アタイは詐欺師じゃない!」警備員が人混みの中から彼女を強く押し出した時、ジャックドーンは駆け寄って警備員を押し返し、アイカを劇場の入り口から引き離した。 「もうちょっとで前金が貰えるとこだったのに」アイカはそう呟いた。「あの女の人、アタイのサックスの音色は綺麗だから、犬もきっと気に入るって言ってくれたんだ。アタイの演奏を聞くとワンワン吠え続けるから、夜は大人しくなるんだって」 ジャックドーンは内心、あの婦人は犬の鳴き声に悩まされていて、アイカの演奏でその犬を殺そうとしているのではないかと思った。彼はアイカを引っ張って、他のホームレスの後に続いた。するとジェリーが二人を追い越し、アイカの肩を叩く。「よう、今夜の収穫はどうだ?」アイカはまた嬉しそうに答えた。「ある女の人が100ディスコインくれるって言ってくれたんだ!もうちょっとで手に入るとこだったから、今夜はもっと運が良くなるはずだよ」「でも、貰えなかったんだろ」ジェリーは肩をすくめた。「みんな元気ないんだ。せっかくのお祝いムードが、警備員に台無しにされちまってさ」 アイカが周囲に目を向けると、確かに活気のない人が多い。あまりに突然追い払われたせいで、ほとんど誰もチップを稼げなかったのだろう。豪華な食事はおろか、新年のプレゼントも期待できない。劇場横の巨大なサイネージ広告は、松の木、星、防寒下着、香水、熱々のローストチキンなど、様々な画像に変化している。そして、広告の歌が何度も何度も流れていた。「ハッピーニューイヤー、明けましておめでとう……」 その途端、アイカは何かをひらめきサックスを取り出した。ジャックドーンは、彼女が丹精込めてサックスを装飾したことにすぐ気付く。銅管は磨き上げられ、どこから摘んできたのか分からないモチノキの枝がベルに2本巻きつけられ、赤いチョコレートのアルミ箔が1枚貼られている。彼女は角のすぐ傍にある銅像に登り、大声で群衆に提案した。「入り口でパーティーさせてくれないなら、ここでやっちゃおうよ!」 ホームレスたちは、言い出したのがアイカだと分かると、大笑いして彼女に歌をせがんだ。アイカが本当に歌い始めると、先ほどまで一番声を張り上げて騒いでいた人でさえ黙ってしまった。アイカは夢中で歌っている。ジャックドーンは必死に聞き続け、その歌が『ニューイヤーの妖精』だと気付いた。それはとてもシンプルな童謡で、5~6年前、まだ旅回りの劇団時代に前座用に作った曲だ。その後、孤児院の子供たちにこの歌を教えたことがあった。歌っていた子供たちの顔が、幸せそうな笑みに満ちていたのを彼は覚えている。 ホームレスたちは、彼女が何を歌っているのか分かっていないだろう。アイカは歌詞を完璧に覚えているが、全ての音が外れている。ジェリーは大声で彼女に尋ねた。「アイカ、『カボチャの鉢にはお歌がいて』って何だ?」 ホームレスたちは笑い声を上げたが、突然彼らの間に優しい声が響き渡った。その声は、とても自然にアイカの歌の続きを歌っていく。「トナカイは荷車を引いて山を下り、リスは忙しなくお引っ越し。カボチャの鉢には子豚がいて、手を叩いて鳴いていた」 童謡の一節を歌い終えると、彼は高音のハーモニーに切り替える。『ニューイヤーの妖精』から、『新年賛歌』組曲の冒頭、そりに乗って森に入る王子の歌に変わった。軽快なハーモニーの下では、音程の狂ったアイカの歌声も、全て美しい童謡の朗読になる。人々は歌に酔いしれ、劇場の入り口にいた人々も集まってきた。遠く雪に覆われた森の景色が彼らの前に現れる。荒野の王子は新年を迎える前に城を去らなければならず、最初はとても悲しんでいた。しかし先導する妖精の後をついていくと、輝くキノコ畑に辿り着く。そこではリスがお喋りをしながら松の実を運び、鳥が歌っていた。王子は微笑んだ。新しい家ができたからだ。 曲が終わるとその場がしんと静まり返る。そして誰かが「ブラボー」と叫び出すと、皆が一斉に拍手を送った。アイカは銅像から滑り落ち、ホームレスたちに受け止められる。ホームレスたちは熱狂して彼女の名前を叫び、誰かがギターを引くと、皆で踊り始めた。観客はどんどん増えていき、人々は蓋の開いたビールや食べ物を渡し合い、食べながら歌っている。コインや花、焼きたての栗、ローストされた大きなガチョウの足までがアイカに差し出された。彼女はたくさんの荷物を抱えて辺りを見回す。たった今、自分と歌声を重ねたのは、彼女が「拾った」酔っ払い男だと気付いたからだ。(あの人、あんなに歌が上手かったんだ!) 「ねぇ、兄さん」彼女はようやく、立ち去ろうとするジャックドーンを人混みから見つけた。「そんなに歌が上手いなら、なんで劇場で歌わないの?そうすれば、アタイみたいに路上生活しなくてもいいのに」ジャックドーンはしばらく下を向いて考えた末に、こう言った。「行きたくないんだ」アイカには理解できなかった。「なんで?アタイは劇場に入るのが夢なんだ。首席演奏家になれたら、どんなに幸せだろうなぁ」 「バカな子だ」ジャックドーンは彼女の頭を撫でる。「俺は今でも十分幸せなんだよ。幸せなら、どこにいたって同じだろ?」アイカは分かっているような分かっていないような様子で頷き、両手いっぱいのコインを差し出した。「ほら、こんなにお金がいっぱいあるから、お酒も買えるよ」彼女は真剣に彼に数えてみせる。「1、2……6……12枚もある!2本も買えるね!」「そうだな」ジャックドーンはその中からコインを数枚取った。「待ってろ、酒を買ってくる」 店から出てきた彼は酒を持っておらず、代わりに丁寧に包装された袋を抱えていた。彼はその袋をアイカに渡し、両手をこする。「ほら、新年のプレゼントだ。さっき劇場のオーナーから貰ってな」 アイカは寒さでかじかんだ手で慎重に包装を解いていく。中にはリードと状態のいいサックスの楽譜があった。アイカが顔を上げると、ジャックドーンは既に遠くへ行っていた。「おーい!」彼女は大声で叫ぶ。 しかしジャックドーンには聞こえていなかった。そこで彼女はリードをサックスに付けて思いきり吹く。 そして振り向いたジャックドーンに手を振り、大声で尋ねた。「お酒は買わないの?」 ボーン――0時の鐘がとうとう鳴り響いた。劇場に集まっていた人々は静まり返り、多くが目を閉じて空を仰ぎ、新年の幸福を祈っている。 ライトに照らされた暗い空はまるで列車が通るトンネルのようで、落ち葉はガチョウの羽のようにひらひらと舞っている。この衣食住にも乏しい人々の祈りが、全能の神に聞こえるだろうか。彼らの祈りの声はあまりにも弱々しく、すぐに劇場の壮大な音楽にかき消されてしまった。 どうやら特別公演の幕が上がったようだ。扉の明かりが、落ち葉の散る地面に金粉を散らす。その特別公演がどのような内容なのか、劇場がファンにどのような神秘的なプレゼントを贈るのか、彼らが知ることは永遠にないだろう。しかしジャックドーンは、特別なプレゼントを手に入れた。 「アイカ」かつての酔っ払い男は、目を輝かせてアイカに手を振った。「あけましておめでとう!」
全文表示
ソース:https://ptn.aisnogames.com/ja-JP/news/94
「無期迷途」最新情報はこちら 無期迷途の動画をもっと見る
セルランの推移をチェックしましょう
無期迷途の動画をもっと見る
セルランの推移をチェックしましょう
| サービス開始日 | 2022年10月27日 |
| 何年目? | 807日(2年2ヶ月) |
| 周年いつ? | 次回:2025年10月27日(3周年) |
| アニバーサリーまで | あと289日 |
| ハーフアニバーサリー予測 | 2025年4月27日(2.5周年)
あと106日 |
| 運営 | AISNOGames |


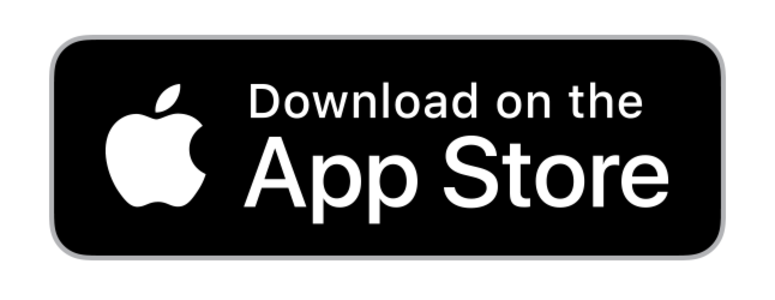
ジェリーという主人公の行動や周囲の状況がリアルに描かれていて、物語に引き込まれます。特に、予期せぬ展開が次々と起こる部分が面白く、読み進めるのが楽しみです。また、登場人物同士の関係性や背景も少しずつ明らかになっていくので、次の展開が気になりますね。