- 少女が紫髪の男と会話をしている
- 男が少女に新しい名前「ロア」を付ける
- 少女は街で新しい服を着て歩く
- 少女は新しい自分に出会ったと感じる
【web小説】流星の尾 -街娘の一日-

お知らせ > その他 [その他] 【web小説】流星の尾 -街娘の一日- 24.11.11 24.11.11 ←前の話へ 狭く薄暗い、しかし柔らかい光が差し込む部屋の中。 「ふむ……」 やや癖がかった金の長い髪を揺らしながら、少女は自身が着ている服を鏡で見ている。 「如何でしょうか?」 スーツ姿に濃いサングラスを掛けた紫髪の男は、少女に問いかける。 「これで余は、疑われないのか? どこからどう見ても、街娘か?」「疑い様がありませんとも」「そうか」 自ら問いながらも、男に素っ気ない返事を返した少女は、どこか落ち着かない様子だった。 胸元に紺のリボンをあしらった襟付きの白いワンピーススカートなど、普段は着る事すら無いのだろう。 少なくとも男は目にした事が無い。少女の置かれた立場がそれを許さない事は、容易に見て取れる。 「どうされましたか?」 男は、少女の出かかった言葉を促すように問うた。 「こんなに軽い服は、落ち着かない」「そうでしょう」「しかし」「しかし?」「……」 少女は言葉に詰まり、一言、絞り出した。 「……かわいい」 それはまるで、花畑の中で一輪しかない花を探し回り、ようやく見つけ出したかの様だった。同じ歳の少女ならば特に考える事も無く無意識にでも口にするだろう、ありふれた賛辞だった。 紫髪の男は微笑み、そして大袈裟に考える素振りを見せた。 「どうした」「いえ。新たなお名前が必要だと思いましてね」 少女は口を開かない。それは何故か、とは聞かない。きっと、その意味を理解している。聡い子だと男は思う。 「どうしましょうかね。陛下のお名前と似ている方が、戸惑わずに済むでしょうから」 狭い部屋の中を、男が腕を組みながら大袈裟に首をかしげ、歩き回る。規則正しい靴の音が聞こえる。 「ロア。街娘のあなたのお名前は、ロアでいきましょう」 ロア。どこかの言葉で精霊を意味すると、後に少女は男から聞いた。王城の書物を調べたもののそれらしき文献は見つからず、その真偽は分からないままだった。 だが少女は、その名前を気に入った。 それは、いつも自分を気にかけてくれる者が付けてくれた名前という理由だけではない。 自分自身も知らない、新たな自分に出会えた気がした。 昼下がりのラグナデア市街は、どこも人で溢れかえっている。 少女は街へ繰り出す前、男から好きに行動して構わないと聞いていた。しかし、街の様子を見た男から、さりげなく右手を差し出された。少女は促されるままに左手で男の右手を握った。ひんやりとした男の手の体温が伝わってきた。 商業地区の道には、行き来する様々な人が居る。 少女と同じ程の背丈をして、片手に風船を持っているミケ族の少女と、すれ違い様に目が合う。 道の両脇には様々な店が並んでいて、カフェ店外のパラソルの下で、ティーカップを片手で取りながら、もう片方の手で身振り手振り、話に夢中になっている身なりの良い婦人同士の愚痴が耳に入る。 暗い路地裏を見遣れば、ぼろぼろの服を着た少年が無気力に座り込んでいる。その隣にいる、同じくぼろぼろの服を着た兄らしき少年に鋭い目で睨まれ、思わず目を逸らす。 盛況している魚売りの店から嗅いだことの無い生臭さを感じ、眉を顰める。かと思えば、今度は焼き菓子の良い匂いが漂ってきて、無意識に匂いの元へと誘われる。 少女はまるで小動物の様に、一つの出来事に対して僅かながら反応を示していく。来て早々、少女はその大きな瞳に入るもの全てを味わっている。 男は少女の手を握りながらもその様子を逐一楽しみ、歩調を合わせて進む。たまに少女の手を少しだけ引き、余所見に夢中な少女にぶつかりそうな人を避ける。 「あれは」 少女は、親に連れられ右脇の店から出てきた少年が持つ何かを、空いた右手で指さす。 円錐の頂点を逆さにした様な、焼き菓子の土台の上に、白いクリームのような何かが渦を巻いているものだった。 「ソフトクリームと呼ばれるものでしょう」「アイスクリームでも、生クリームでも無いのか」「どちらかと言えば、アイスクリームに近いものと聞いています」 俺は食べた事がありませんがね、と男は付け加えた。少女は少年の持つソフトクリームに目を奪われ、少年が通り過ぎると代わりに店の看板を眺めた。 「食べたいですか?」 紫髪の男は、少女の嗜好を知っている。少女は、甘いものに目が無い。何とも愛らしいではないか。 「いいのか?」「勿論ですとも」「頼む」 紫髪の男は少々ここでお待ちくださいと少女に言って店の前に立たせ、店の中に入って行く。 少女は男の言われた通りに待ちながら、行き交う人々を、あるいはその流れを、目で追う。 その時だった。 「お嬢ちゃん」 少女はその言葉が自身に掛けられているものだと気付くのに数秒かかった。そしてそれを悟ると、遅れて驚き、左右を見た。 振り返ると、店の看板と同じロゴが入ったエプロンを着る熟年の女が立っていた。 「パパかママを待っているのかな?」 少女の視線まで屈み、満面の笑みで女は言う。 ――何故、この人は自分に話しかけたのだろう? 少女はどう答えればいいのか、全くわからない。 ただ黙って、女の瞳を見つめ返す事しかできなかった。 「どうしたの?」 女は相変わらず笑いながら話す。これにも少女は、どう答えたらいいかなど分からない。 「もしかして、迷子かな?」 街娘とは、このような時にどう答えるべきなのか。 少女は自らの浅い経験を手繰り、答えを探すが、見つからない。思考がぐるぐると空回りをする。無意識に、僅かに首を振っていた。 少女がまだ知らない純粋な善意は、少女にとっては劇物だった。 少女は知らなかった。人が人に向ける、何気無い善意を。大司教の女の傀儡として、そのようなものを向けられた事など無かったから。 目の前の女の笑顔から目を背けられない。脳裏で、恐怖の象徴である大司教の女の不気味な笑顔と重なっていく。 少女の心は、この場に居もしない大司教に再び支配されようとしていた。もう、何も考えられなかった。 「心配しなくていいから、パパやママが来るまで、お店の中でゆっくり」「いやあ、ご心配をお掛けしたようで」 女の言葉が途中で別の声に遮られ、少女は唐突に現実に引き戻された。二人が同時に声の主の方へ振り返ると、紫髪の男がソフトクリームを片手に立っていた。 「友人の子を預かっていましてね」 女は立ち上がり、男からどう思われるかも気にする素振りも見せず、男の全身を足元から眺める。 女の視線が男の長く尖った耳に至った時、再び女は少女の視線まで屈み、今度は小声で少女に耳打ちする。 「そうなの?」 少女は答えず、代わりに大袈裟に首を縦に振った。その様子に理解を示したのか女は立ち上がり、男の方へ振り返った。 「お買い上げ、ありがとうございました」 女は一礼して、空いた左手で会釈をする男の横を通り過ぎ、店の中に入って行く。 すれ違う際、なおも自身に若干の不信感を募らせる女の様子を横目に、男は少女にソフトクリームを手渡す。 そして、空いている店外のテーブルの椅子を引き、少女の着席を促した。 「随分とお待たせしてしまったようで。ちょいと人が多くて」 男は肩を竦ませながらも、笑った。少女は男に促されるままに座り、男もまた、少女の向かいに座った。 「怖かった」 少女は、ソフトクリームを眺めながら呟く。真っ白で冷たいそれは日差しに晒され、早くも溶け始めていた。 「そうかもしれませんね。今のあなたには」 男は少女に、溶けかかったソフトクリームを早く食べるよう、目で促す。 「ですが、彼女はあなたに純粋な善意で語りかけていたのです。おそらくは、あなたが迷子ではないのかと」 少女は男の顔を見る。男は、いつもの笑みを浮かべている。彼が言うのであればそうなのだろう、と思う。 「あなたはこれから多くの人と出会うでしょうし、むしろ積極的に出会うべきです。我々とだけではなく、我々が守るべき人々とも」 男は周囲を見渡しながら、なおも語る。 「彼等が何を思って、どう生きているのか。あなたは人の上に立つ者として、そんな彼等の気持ちに触れ、彼等の気持ちを知っていくべきです」 少女は男の話に耳を傾けながら、溶け始めたソフトクリームの先端を舐めた。 「まあ……。そのうち、彼女があなたに話しかけてきた意味も分かるでしょう」 ソフトクリームは冷たく、そして甘かった。 陽が沈んだ頃、商業地区を二周してすぐ、少女の耳に噴水広場の方から荒い演奏の音と人々がばらばらに歌う声、そして喧噪が聞こえてきた。 少女はそろそろ王城へ帰るべきかと言おうとしたところで、にわかに聞こえだしたその音に興味を惹かれ、言葉を呑み込んだ。 今日という日が、少女にとっては一年間の中でも滅多に無い、執務の無い日で良かった、と少女は思った。――とは言え、その帰りが遅くなれば、王城で騒ぎが起きるであろう事は、想像に難くないのだが。 「折角ですから、見て行きましょうか」 男は少女に語りかけた。街灯が灯される前だからか、男の表情は影でよく分からない。 噴水広場に近付くにつれ、昼とはまた違う光に包まれている事に気付いた。 周囲を見れば、幾つものテントが張り巡らされ、そのいずれにも明かりが付けられている。 人に至っては昼よりも多く、そして各々乱雑に、好き放題に道を行き交っている。当然、人が増えれば騒々しさも昼の比ではない。というより、その性質が異なるように感じた。 酔っぱらっているのか、ラグナデア万歳、と斉唱する男達の声が耳に入った。 少女ははぐれないように紫髪の男の右手を強く握りしめ、男の足に縋るように歩く。 「人が多い場所は、まだ怖いですか?」 優しい声色で男は問う。 「怖い。人がわからない。不安だ」 一つひとつ、ぽつり、ぽつりと、少女が胸中を語る。 「率直な感想で何よりです」 男は微笑んだ。 「知らない人ばかりですからね。そんな中に居るのは、始めは恐ろしく感じるのでしょう」「そう。そうだ」 少女は男の言葉を肯定する。まるで生まれたての赤子の様な純粋さだ、と男は思う。 「ですが、見てください」 男は、手近のテントを指す。視線を追うと、老人と若者が、ビール瓶をぶつけ合っている。母親らしき者が子供に串に刺したソーセージを渡し、子供はそれを頬張る。皆、笑顔だ。 男はそのまま、噴水広場の方を指す。少女がつられて見る先には、音楽に合わせて人々が跳ね、あるいは踊っている。 それは王城で演奏されるような洗練された、上等な音楽では決して無く、上手とも言えない。更に言えば、ところどころリズムも音程も狂っているし、それを勢いで誤魔化している。それでもそれは、音楽と呼べた。 そんな音に合わせて身体を動かす人々も、てんでばらばらな動きをしている。少女の視線の端で、抱き合って踊っていた若い男女の足がもつれ、情けなく転ぶ。しかし、起き上がろうとする男女も含めて、誰もが笑顔だ。 「皆、笑っていますよ」 紫髪の男もまた、微笑んだ。街灯の光で、こちらを見下ろす男の美しい陰影が、はっきりと見えた。 人々が祭典を楽しむ様は、少女が短い人生で見てきたどんな光景より温かさに包まれていた。それに躍動的で、何よりも命に溢れていると思った。 人々は、大司教の――いや、それに従わされていた自身の圧政に苦しんでいたはずなのに。 少女は、自分が何故人混みを怖がっていたのか、その理由を考えていた。 この笑顔が溢れる街の片隅で、自分は何を怖がっていたのだろうと。 少女が口を開こうとすると、何かが空に飛んでいく音がした。次の瞬間、破裂音と同時に光が夜空を舞った。 「わあ……」 少女から、感嘆の息が漏れた。 花火は少女にとって、初めてのものでは無かった。祭典の様子など、王城からは小さな数多の光でしか判別できなかったが、花火は違った。 花火は王城から、見下ろすように眺めていた事があった。その時は、ちっぽけな光の集合体が広がって散っていくだけの、取るに足らないものに見えた。 しかし今、自分は花火を見上げている。腹の底に響くような音と共に、色とりどりの光が舞い散る様を見上げている。 人々の歓声と共に、自分も喜びの声を上げている。 何故かはわからない。少女は、この瞬間を誇らしく思った。気付けば、目頭が熱くなった。 「カルシオン」「何でしょうか?」 カルシオンと呼ばれた男が少女の視線まで屈む。その微笑みを真っ直ぐに受け止めて、少女もまた微笑んだ。 「また、来よう」 ←前の話へ
全文表示
ソース:https://forum.gransaga.jp/#/view/4/1040
「グランサガ (Gran Saga)」最新情報はこちら グランサガ (Gran Saga)の動画をもっと見る
セルランの推移をチェックしましょう
グランサガ (Gran Saga)の動画をもっと見る
セルランの推移をチェックしましょう
| サービス開始日 | 2021年11月18日 |
| 何年目? | 1140日(3年1ヶ月) |
| 周年いつ? | 次回:2025年11月18日(4周年) |
| アニバーサリーまで | あと321日 |
| ハーフアニバーサリー予測 | 2025年5月18日(3.5周年)
あと137日 |
| 運営 | Npixel Co., Ltd. |

 3人のキャラクターでチームを組んで戦おう!
魅力あふれる騎士団のメンバーたちから3人を選んで、メンバーを切り替える「タッグバトル」や、残りの2人を指揮しながら協力する「チームバトル」で戦おう!
3人のキャラクターでチームを組んで戦おう!
魅力あふれる騎士団のメンバーたちから3人を選んで、メンバーを切り替える「タッグバトル」や、残りの2人を指揮しながら協力する「チームバトル」で戦おう!

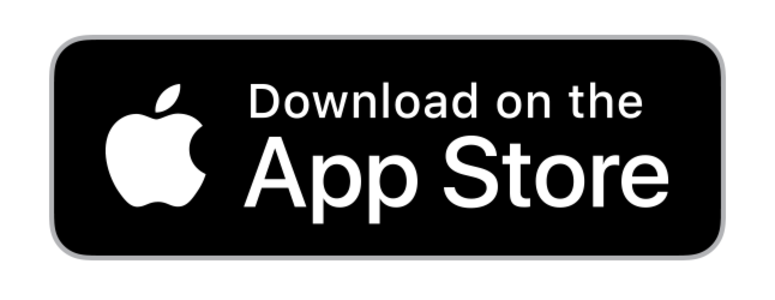
少女が紫髪の男に名前を付けてもらうシーンなど、どこか幻想的で不思議な世界観が感じられました。物語の展開が気になります。